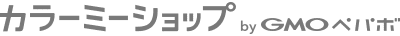江戸時代前期は、九谷焼が誕生した時期です。
九谷焼は、大聖寺藩 初代藩主の前田利治のもとで、1655年に作り始められた磁器です。鉱山開発の最中に、領内の九谷村で陶石が発見されたことがきっかけとなり、伊万里焼の技術を導入して、磁器の生産を始めました。陶石の産地となった九谷村に窯を築いたことで、その地名にちなんで「九谷焼」と呼ばれるようになりました。
特にこの時期に作られた九谷焼は、後世「古九谷」と呼ばれ、その青手や色絵の美しい絵付けのスタイルとともに、磁器の職人や知識人たちの間で特別視される名作として、大切に受け伝えられてきました。
しかし、古九谷は制作開始からおよそ50年後に、突然生産が終わってしまいます。大聖寺藩の財政難による資金不足や、藩主の代替わりで政策の方針転換など、制作終了の明確な証拠は見つかっておらず、今日まで「謎」として残されたままです。